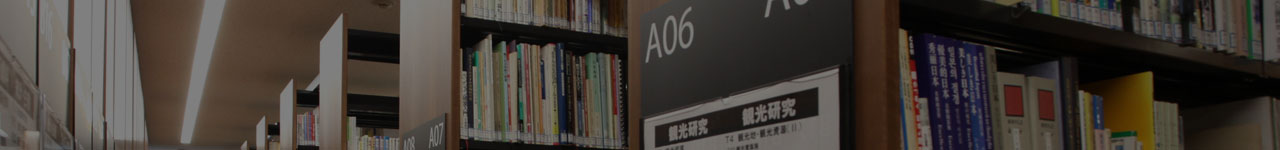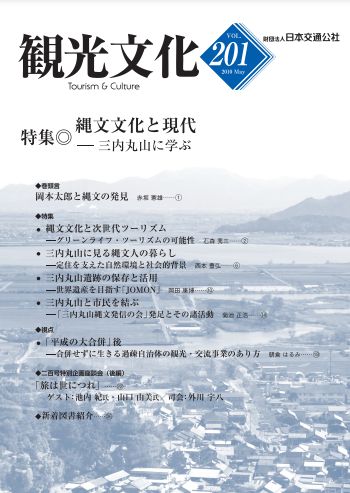[巻頭言〕岡本太郎と縄文の発見 東北芸術工科大学東北文化研究センター所長 赤坂 憲雄
あの『太陽の塔』を創った前衛芸術家・岡本太郎こそが、紛れもなく縄文文化の発見者であった。それはしかし、意外なほどに知られていない。いや、忘れられたと言うべきか。戦後間もない、晩秋のことだった。太郎は上野の東京国立博物館で、縄文の土器のかけらや土偶との衝撃的な出会いを果たした。それを「四次元との対話─縄文土器論」と題した論考に仕立て、『みづゑ』という美術雑誌に発表した。センセーショナルな反響を呼び起こした、という。それから、六十年ほどの歳月が過ぎている。
例えば、ここにいう「発見」とは、何を意味しているのか。それは取りあえず、モノやコトに対して、新たな知の文脈に根差した意味の付与を行うことである。近世に、第一の発見があった。十八世紀の末、紀行家の菅江真澄などは、土器片のスケッチを残し、「縄形、布形の古き瓦」「網代らしき紋様」といった観察を行い、「いにしえの蝦夷」が作ったものかという推測まで書き留めていた。第二の発見は、アメリカの考古学者・E.S.モースによってなされた。大森貝塚の調査・研究の中で、「縄紋」の紋様を持つ土器について記述し、「縄紋土器」という名付けの先駆けをなした。縄文考古学の幕開けである。
そして、第三の発見が岡本太郎その人によってなされる。太郎はいわば、縄文土器そのものとの対話を試みたのである。そこに縄文人の美学を認め、それを世界観の結晶として読み解こうとした。強烈な表情、激しい流動性、シンメトリーの拒絶、破調、ダイナミズム、混沌、無限の回帰と逃走、……狩猟文化の影。縄文土器を単なるモノとしてではなく、縄文人の心や精神が宿りするウツワとして眺めること。太郎はまさに、縄文土器に新たな命を吹き込み、縄文人の精神世界を甦らせたのである。
その発見の舞台が東京国立博物館であったのは、偶然ではない。若き日、パリに留学していた時に、太郎はマルセル・モースの下で本格的に民族学を学んだ。この民族学を光源として、縄文文化が発見されたのである。単なる芸術家の思いつきや直感ではない。未開社会の仮面や神像の中に隠されている、豊かな精神世界を解読する方法を、太郎は知っていた。だからこそ、縄文土器に対して、民族学の方法をもってアプローチすることができたのである。縄文文化は今、第四の発見の季節を迎えているのかもしれない。
(あかさか のりお)
掲載内容
巻頭言
| 岡本太郎と縄文の発見 P1 | 赤坂 憲雄 |
特集 縄文文化と現代―三内丸山に学ぶ
| 特集1 縄文文化と次世代ツーリズム ―グリーンライフ・ツーリズムの可能性 P2 |
石森 秀三 |
| 特集2 三内丸山に見る縄文人の暮らし ―定住を支えた自然環境と社会的背景 P6 |
西本 豊弘 |
| 特集3 三内丸山遺跡の保存と活用 ―世界遺産を目指す「JOMON」 P10 |
岡田 康博 |
| 特集4 三内丸山と市民を結ぶ ―「三内丸山縄文発信の会」発足とその諸活動 P14 |
菊池 正浩 |
| 視点 「平成の大合併」後 ―合併せずに生きる過疎自治体の観光・交流事業のあり方 P18 |
朝倉 はるみ |
| ◆二百号特別企画座談会(後編) 「旅は世につれ」 P22 ゲスト:池内 紀氏・山口 由美氏/司会:外川 宇八 |
|
| 新着図書紹介 P36 |