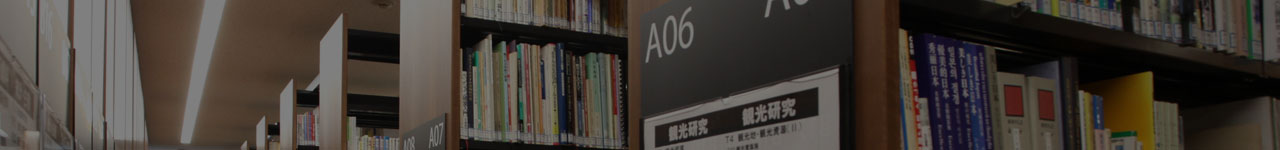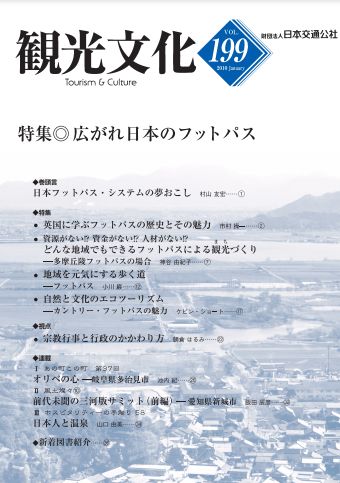広がれ日本のフットパス (観光文化 199号)
特集 : 広がれ日本のフットパス
ここ数年、中高年を中心にウオーキングブームが続いています。昨今よく聞かれるようになった「フットパス」とは、森林や田園地帯、古い町並みを楽しみながら歩く小径のこと。今号では、発祥地である英国のフットパス発達の歴史、地域活性化・観光振興を目的としたフットパスの活用を目指す国内の活動などを紹介します。
- 発行年月
- 2010年01月発行
- 判型・ページ数
- B5判・36ページ
- 価格
- 定価1,540円(本体1,400円 + 税)
※本書は当サイトでの販売は行っておりません。
[巻頭言〕日本フットパス・システムの夢おこし 社団法人 日本ウオーキング協会会長/歩行文化研究所所長 村山 友宏
ついに日本にも、草の根市民活動の中からフットパスづくりの全国連携が始まりました。その歴史的意味は限りなく大きく、欧米の“歩きみち”を歴訪し、日本でもぜひ世界に発信したいニッポンのふるさと・地域の誇りをユニバーサル・フットパスで日本列島をつなぐ夢を追ってきた者としては感慨ひとしおです。
歩くことが人間の限りなく豊かな営みであることに気付かないのは便利漬けの現代人の通弊ですが、歩くことを楽しむ“歩きみち”が社会資本として重視されていない国は、先進国の中では日本だけのようです。
ウオーキングの実践が健康・環境・観光・教育・交流の5K分野に社会貢献することが知られ、またウオーキング志向人口が国民の五一%に達した今(二〇〇九年九月内閣府世論調査)、ウオーカブル日本、ウオーカブル都市をどうつくるかは、まさに時代のテーマです。
フットパスづくりはハード先行の土木事業ではなくソフトな生活文化事業です。フットパスづくりの原則は、?官民連携でも歩く人が主体、?地域の誇りのネットワーク、?公共交通機関とのアクセスの配慮、?明解な道標とマップ、?体力に応じて選択可能なコース設定、ユニバーサルの配慮、?地元の十分な理解、?環境や住民の生活静穏を守る利用ルール、?道を守り育てる利用者責任の仕組み。アドプト制度・歩くみち守り・フットパス・レンジャー等、?地域調整役のフットパス・コーディネーター(道中奉行)の設置、?将来はコースを広域ネットワークし、先人の足跡やニッポンのふるさとをネットワークする日本フットパス・システムへのリンクを視野におく、等が望まれます。
欧州大陸にはE1?11 の長距離フットパスがあるように、米国にも一九六八年ナショナル・トレイル・システム法ができ十七本のナショナル・トレイルができています(日本の東海自然歩道はこのうちトレッキングコースのアパラチアン・トレイルがモデル)。
十四、五年前に私どもは米英独の“歩きみち”を二年間現地調査し、その事例を『ウオーキング・トレイルのみちしるべ』として出版しました。建設省に提言した「ウオーキング・トレイル事業」は一九九六年から始まっています。
その後、私どもは二〇〇四年に国土交通省後援で「美しい日本の歩きたくなるみち」500選を公募し実踏選定したところ利用者は年間九百万人を超えました。この勢いを得てさらに国際級の「日本フットパス・システム」の実現をめざし、各地のウオーカーやベテランのユースホステラーたちとともに実踏調査を始めています。
“気持ちよく楽しく歩ける”地域づくりへの住民参加は地域活性化の引き金となり、日本の魅力を旅して歩く「日本フットパス・システム」づくりは観光立国の大きな礎となるはずです。さあ、各地で「日本快歩列島」夢おこしの一歩を!
(むらやま ともひろ)
掲載内容
巻頭言
| 日本フットパス・システムの夢おこし P1 | 村山 友宏 |
特集 広がれ日本のフットパス
| 特集1 英国に学ぶフットパスの歴史とその魅力 P2 | 市村 操一 |
| 特集2 資源がない!? 資金がない!? 人材がない!? どんな地域でもできるフットパスによる観光づくり ―多摩丘陵フットパスの場合 P7 |
神谷 由紀子 |
| 特集3 地域を元気にする歩く道 ―フットパス P12 |
小川 巌 |
| 特集4 自然と文化のエコツーリズム ―カントリー・フットパスの魅力 P17 |
ケビン・ショート |
| 視点 宗教行事と行政のかかわり方 P22 | 朝倉 はるみ |
◆連載
| 連載I あの町この町 第37回 オリベの心 ―岐阜県多治見市 P26 |
池内 紀 |
| 連載II 風土燦々(10) 前代未聞の三河版サミット(前編) ―愛知県新城市 P32 |
飯田辰彦 |
| 連載III ホスピタリティーの手触り 58 日本人と温泉 P34 |
山口由美 |
| 新着図書紹介 P36 |