“観光を学ぶ”ということ
ゼミを通して見る大学の今
第6回
北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院
国際広報メディア観光学専攻 観光創造コース
西山ゼミ
観光は地域で創造される。
取り組むべき課題は地域の住民や事業者、自治体職員が真剣に悩んでいる問題の中にこそある。

西山徳明(にしやまのりあき)
北海道大学観光学高等研究センター教授。京都大学工学部建築系学科卒。同工学研究科修士課程修了、同博士課程単位取得認定退学。博士(工学)。九州芸術工科大学教授、九州大学教授、国立民族学博物館客員助教授などを経て2010年から現職。主な研究領域は建築・都市計画学、ツーリズム、文化資源マネジメント、観光開発国際協力。公職として文化審議会分科会専門委員(文化庁)、国土審議会専門委員(国交省)、竹富島伝統的建造物群保存地区等保存審議会委員(竹富町)、白川村景観審議会会長(白川村)、太宰府市景観・市民遺産会議委員、(太宰府市)、公益財団法人日本交通公社専門委員など。
北海道大学大学院
国際広報メディア
観光学専攻
観光創造コース
「北大観光」と呼ばれている私たちの大学院は、2007年に「観光創造専攻」として修士課程・博士課程が同時設置され、12年間で修士修了生160名以上、博士10名以上を輩出し、2019年度からは標記のような1専攻2コースの内の観光創造コースとしてリニューアルしたばかりである。
本専攻・コースの特徴は、ややもすると実業系と理論系の専門が分離しがちな日本の観光研究の世界に一石を投じるべく、「観光は地域で創造される」との考えの下に「地域」をキーワードとして研究・教育を展開する点にある。そのために、「価値共創」「地域協働」「国際協力」の3つの教育領域を立て、様々な地域の観光創造の場への学生の参画を促し、実践的な教育を推進してきた。
デスティネーション・マネージャー育成プログラム
北大観光の近年の取組みでもう一つ特筆しておきたいことがある。それは、「明日の日本を支える観光ビジョン」において打ち上げられた諸施策の内、高度観光人材育成に関するMBAプログラムに注目が集まる中、北大観光は、地方地域におけるDMO人材の育成の重要性を説き、MBAと対(つい)になって明日の日本の観光を支える「デスティネーション・マネージャー」の育成ログラムを、主として社会人を対象に2017年より開始したことである。現在3期生がデスティネーション・マネージャーとして巣立つところであるが、北大観光のめざす観光創造をまさに前線で実践してくれる貴重な人材たちである。
北大観光とゼミ
筆者のゼミでは、前記のような観光創造の取組みの中でも特に「観光デザイン」を標榜し、①地域における観光資源の発掘、保存、保全、創造、インタープリテーションなどの資源マネジメント研究(価値共創)、および②観光まちづくりを地域で実践する上で不可欠な各ステークホルダー間の調整を行う組織マネジメント研究(地域協働)を、専攻・コース内の観光マーケティング専門家と協働して行ってきた。そして特に、③JICAとの共同で、その実践の場を海外の発展途上地域に求め、JTBF等の民間研究機関との産官学協働による観光開発国際協力にチャレンジし、成果を残してきた点は広く評価を得ているところである(国際協力)。
ゼミ運営の背景
筆者は、1995年度から15年間を九州大学(2003年合併までは九州芸術工科大学)芸術工学部環境設計学科で、そして2010年度から今日までの10年間は現在の北海道大学でゼミを主宰してきた。本稿では、この四半世紀の間、私と一緒に地域に向き合って頑張ったゼミ生たちによるフィールド研究の事例を振り返りながら、彼らが何に関心を持ち、学び、感じているのかについて考えてみたい。
自身の出身は建築学の都市計画であり、学生であった1980年代後半より、沖縄の竹富島や飛騨の白川郷(現在の世界文化遺産白川村荻町)、木曽の妻籠宿等をフィールドに、「町並み保存」および、いま言うところの「CBT=community based tourism」について研究を開始した。町並みという景観を保存・保全するには、伝統的建造物群という文化財の価値発掘に関わる分野である建築史・都市史学、そして景観という有機的な存在を管理対象として構造的に把握するための景観工学を理解し、その価値や構造を条例や補助金といった現代の法制度を駆使して保全、維持、継承するシステムを構築する専門性(都市計画学)が必要となる。こうした町並みに留まらない様々な観光資源の保存やインタープリテーション、活用等に係る複合的な専門性を指し、私は(観光)資源マネジメントと呼んでいる。
一方で私が資源マネジメント研究を始めた当初から直面した問題があった。それは、町並みという文化財の保存・保全には、そこに人が住み続け、コミュニティの活力が持続することが必須であるが、そのために町並みという資源を損なわずに活用して稼ぐ方法論の欠如、すなわち観光という特異な市場原理の中で商品を造成し販売するという実務的な観光マーケティングの専門性が地域に欠如していることである。
九大時代は観光マーケティング研究の重要性を認識しつつも縁遠く、北大に移ってから多くのいわゆる観光学、観光マーケティング学の専門家とともに、美瑛町や札幌市を始めとする道内の観光先進地、およびJICAの技術協力のスキームを通じてエチオピアやヨルダン、ペルー、ジンバブエ、フィジー、イランといった途上国の観光開発国際協力の現場を経験することができた。特に途上国において、一からの観光開発に携わることを通じ、実践としても理論としても観光マーケティングの重要さと方法論を学ぶことができ、これが私にとっては幸いであった。
実は、この九大の最後の数年から北大にかけての私の貴重な体験を一緒に共有できたゼミ生が7人ほどいる。九大のゼミと北大のゼミまたは教員・研究員等を両方経験できた人たちで、いずれも現在は大学教員やシンクタンク研究員等になって観光研究の第一線で活躍している。
ゼミ運営の方法
高校までの学校では教科書にある正しい答を学ぶが、大学や大学院は研究するところである。そして私たちのような計画学のゼミで行うべき研究とは、社会で未だ解決できない諸課題の解決方法を考える問題解決学である。したがって、当たり前のことではあるが、私が主宰してきたゼミでは、答のわかっている課題を学生に出したことはない。
前述した私自身の観光研究の発展プロセスは、多くのゼミ生たちと共有してきたプロセスでもあった。私は学生たちと同時に育ったと言ってよい。そうした私がゼミ生を指導する際に最も心がけたことは、研究対象とする地域課題を私自身が理解するプロセスの、なるべく上流から学生を参加させるということである。社会との接点は教員だけが持ち、教員のフィルターを経て整理された課題をゼミで学生たちと共有することは避けた。私たちが取り組むべき先端的な研究課題は、本や雑誌の中にも大学のゼミの議論の中にもなく、それはフィールドにしかない。取り組むべき課題は地域の住民や事業者、自治体職員が真剣に悩んでいる問題の中にこそある。
そうした悩める地域からの要請や相談に応えるべく、それが依頼であっても押しかけ調査であっても、研究プロジェクト立ち上げ時にはそうした関係者と打合せをするのが通例であり、そのなるべく初期の段階から興味がマッチしそうなゼミ生を同席させ、私自身が先方から受ける/持ちかける相談を同時に学生にも聞かせ、同じスタートラインに立って共に悩むのである。これは意外に難しい。専門家といえども学者・研究者の知識や知恵は限られたもの、世間知らずであり、一方で住民や行政の有する現場知は力があり深い。想定外の問い掛けや質問に右往左往して学生の前で恥をさらすことは大きなリスクであり、そうした修羅場はできれば避けたいのが人情と言えよう。
ただ、ゼミ生本人がその場に同席したことの意味を少しでも理解できたら、その効果は計り知れない。打合せ後に「どう思った?」「さあどうしようか?」と研究の進め方について相談を始めた際、学生のその研究プロジェクトに対するオーナーシップはすでに膨れ上がっており遺憾なく発揮されることとなる。
前記7名のゼミ生たちの数例を述べて、本稿を閉じたい。
世界遺産白川郷集落
最初の事例は、筆者が学生時代の1987年から押しかけ調査で通っていた白川村である。1995年に世界遺産に登録され、入込み客が年間60万〜70万人から一気に150万人以上に膨れ上がったことで、2000年頃には毎年かなりの日数、地域内や周辺、高速道路本線までも巻き込む大渋滞が発生し、一方で現金収入を得るため世界遺産地区内の大切な田畑をつぶして駐車場にする住民も現れるなど、大混乱が生じていた。筆者は地元保存会と自治体からの要請を受け、ゼミ生数名とともに現地に入った。住民間や、住民と行政間の軋轢など、生々しい問題を一緒になって共有した。その後も数度訪問し、関係者と当方ゼミとで様々に議論した結果、自治体と住民が心から合意できる世界遺産マスタープラン(いまで言うマネジメントプラン)を策定すべきとの結論に行き着いた。修士研究から白川村に取り組んでいたゼミ生の1人が自らの博士研究のテーマとして取り組むことを決め、地域に住み込んで研究に没頭した。3年がかりとなったプラン策定のための30回を超える住民会議や10数回の関係組織の会議全てに資料を作成して出席し、会議録を積み重ねることでマスタープラン策定に貢献、住民主体の景観マネジメントをテーマに博士号も取得した。その後も北大で特任教員として白川村との包括連携協定を担当しつつ、景観計画や観光プラン策定など、地域や自治体からの信頼を得て実戦的な研究を続け、現在は北大を離れ、正規の大学教員として活躍している。

萩まちじゅう博物館
二つ目は萩市の事例である。2000年頃、萩博物館の建替えを契機に、萩市全域をエコミュージアムにする「萩まちじゅう博物館」(まち博)構想を立ち上げることとなり、2004年開館前後のそれぞれ数年間にわたり、4名のゼミ生が間をあけず順に担当、住み込みあるいは通って、この構想実現の過程に参画、その成果を修論、博論にまとめている。最初のゼミ生は、まちなみ保存の興味から武家屋敷地区の伝建見直し調査に住み込みで挑み、修論を書き、修了後すぐにNPO萩まちじゅう博物館に就職して、今もまち博の推進に貢献している。2人目のゼミ生は、まち博の構想・基本計画・活動計画策定を通してエコミュージアム・システム構築に関する研究を修論にまとめ、まち博の立ち上げに貢献し企業に就職した。3人目はまち博を市民が展開するための方法論に関する修論をまとめ、まち博マニュアルを市民のために残した後、他地域のまちづくりNPOで活躍中である。そして4人目は、まち博の最初のサテライトである浜崎という港町に住み込んで当該サテライトの立ち上げに参画し、地域のおたから探しやマップづくり、サテライト博物館の展示等への住民参画に関する研究を修論にまとめ、さらにその萩の技術を、博士課程時代はJICA青年海外協力隊(2008〜10年)として、また北大特任教員時代(2011〜17年)は JICA技術プロジェクトの専門家として参画し、サルト(ヨルダン国)という歴史都市のエコミュージアム開発に技術移転する研究に昇華させ博士号を取得した。現在は国家公務員として文化観光施策に従事している。

世界遺産レブカ(フィジー)
三つ目はフィジーの事例である。筆者は2003年からフィジー国のレブカというイギリス植民地時代の首都であった港町を世界遺産にしようとする当該政府のプロジェクトを研究面から支援すべく、何次かにわたり科研費やACCUの支援事業を使ってゼミ生中心の調査団を組み派遣してきた。2005年、1人のゼミ生が学部4年でゼミに配属されるとすぐにこのレブカ研究に手を上げた。その後の修士・博士課程を通して所期の研究を続け、その成果が採用されて2013年にレブカは「レブカ歴史的港湾都市」として世界遺産リストに登録され、その後もレブカのまちの観光・遺産マネジメントに継続して取り組んでいる。当該ゼミ生は、北大で博士号を取得後、特任教員としてエチオピア、フィジー、ペルー等のJICA国際協力事業を中心的にマネジメントしてくれた後、北大を離れて正規の大学教員として世界遺産等に関する先端研究や国際協力を続けている。他にも、フィジーに住み込んで文化遺産保存の難しさと矛盾を学び、その悔しさを日本の文化財保存の現場にぶつけて活躍するゼミ生や自治体でまちづくりに生かしているゼミ生もいる。
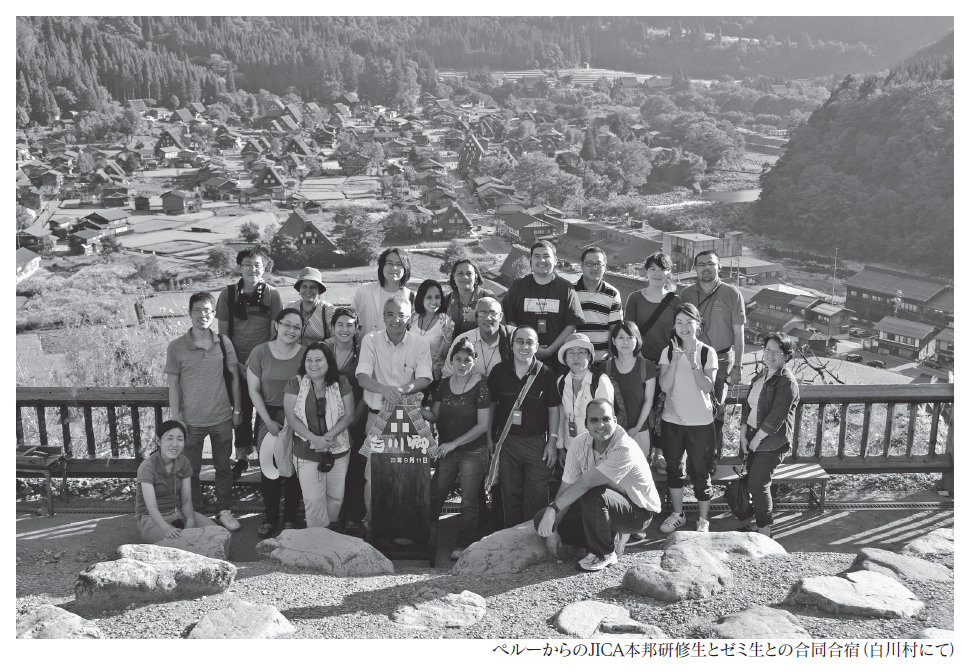

地域が育ててくれる?
上記以外にも、竹富島の遺産管理型NPO立ち上げに参画した経験を生かし大学教員として活躍するゼミ生やJTBFにお世話になったゼミ生、陶芸の里や離島に住み込んで地域の文化的景観という観光資源の見出し方を博士論文にまとめ、シンクタンクでまちづくりに活躍するゼミ生など、ここで書ききれない多くの事例がある。
彼らはみな、自ら関わる地域を大好きになり、その未来を深く憂い、地域の人のささやきや叫びを聞いて課題にめざめ、それを何とか解決し期待に応えたいと考える。しかしその現実と、大学や本で学ぶ理論、よかれとして持ち込まれる法制度の理想や仕組みとのギャップを学び知ることとなる。自分自身の力不足を感じるであろうし、一方で自分のゼミの持つ社会的使命や専門性は何なのかについて改めて考えるのだろう。その苦悩や努力の先に、地域の人たちと共有できるゼミ生それぞれにオリジナルな回答を見出してくる。
私の感じるところ、ほとんどの事例において、まじめに取り組むゼミ生に対して地域の人々は非常に寛大であり、優しく、有り難いことに期待してくれる。最初のボタンさえ掛け違えなければ、必ず彼らは成長し、自分らしい骨太な専門性を身につけるのである。
次年度からも、本ゼミの社会人学生が竹富島に飛び込んで、地元に受け入れられればではあるが、DMO研究に取り組む予定である。残された教員人生で、どれだけのゼミ生を地域と結びつけ、たくましいデスティネーション・マネージャーや観光創造研究者を育成できるだろうかと考える今日この頃である。
